これは今のうちに登録すべきかも。に蠱惑され、其の場で導入を決定し、 実際に使用して見て数日の感想を当アーティクルに記せば、 導入時及び使用開始時の操作感は Dropbox が些か上の様に感じたのは、 偏に直観的に進捗するか否かにあり、 Dropbox では全く戸惑うことなく常用する迄に到れば、 個人的に livedrive は其処迄には至らぬ様に感じた上からなるも、 とは云え2008年12月5日の当ブログアーティクル 愈々評価の高まるDropbox にも記した如く凡そ使い切ると云うには遠ければ、 幾分当てにはならぬインプレッションにて、 Dropbox では充分なβ期間を過ぎた上での使用に加え、 定量的なデータも揃わぬ上では、 Dropbox も使用した上での田口氏の決定版との言説も合わせ、 興味のお有りの方は導入を検討されるが吉かと存知ます。
Livedriveは(ベータ版のうちは)無料かつ容量無制限のオンラインストレージだ。
但し、導入に際し気になる点と云えば紹介記事引用にもあります様に、 無料かつ容量無制限 とあるサービスも ベータ版のうちは との但し書き付きにて、正式版への移行時への保証はなく、 無料にてサービスへの依存を高めておいて正式リリース時に課金するは、 常套にして正当な手段なれば、当該点ともう一つ、 登録時には通常の無料サービスでは余り見られない、 メールアドレスだけに留まらない、 本名、現住所抔、 個人情報を提供することの二つが懸念材料として上げられる様に思います。
実際に登録、使用して見た上では、 先ずは Dropbox と同様にローカルで使用する際には専用ソフトウェアのインストールが必要となり、 この段取りを踏めば Dropbox ではローカルのPC上では特定フォルダで定義される利用スペースが livedrive に於いてはL:ドライブとして定義されますが、 オンラインデータと同期を取り乍、定義スペースが最新データに更新される点は同様となります。
ローカル上では問題無く同期の取れるデータも、 オンライン、Web上の操作に於いては、 上手く日本語での操作が通らぬ点は、 流石に未だβ版とて無理からぬ処か、下記
We are currently experiencing problems with file uploads/downloads, engineers are investigating. 。が如きアラートも表示されたりはすれども、 オンラインストレージサービスには向後益々の期待を寄せる身としては、 其の雄たる候補の当 livedrive には活躍を望み乍、使用を暫く継続、 折有らばレポートを当ブログに供したいと思っています。
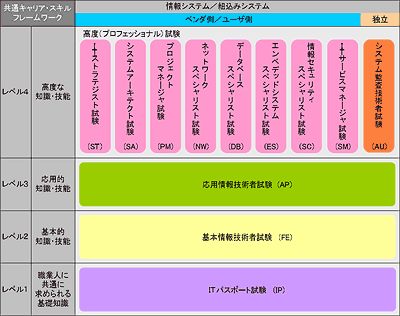
 コードを其の儘コピペで使用出来ますので非常にお手軽で、
画像の配置したパスを考慮するのも面倒にてコードの設置同フォルダに突っ込めば後は特に考えることも無く、
画像名を入力してCREATEボタンを押下するだけで生成のなれば、
ローカルのPHP環境で、
実際に当ブログマスコットキャラクターの
はなまる
君の左なる元画像を変換して表示したものが下になりますので、
範囲選択反転、ブラウザの拡大機能を利用する抔して確認されてみられるのも一興と存知ます。
コードを其の儘コピペで使用出来ますので非常にお手軽で、
画像の配置したパスを考慮するのも面倒にてコードの設置同フォルダに突っ込めば後は特に考えることも無く、
画像名を入力してCREATEボタンを押下するだけで生成のなれば、
ローカルのPHP環境で、
実際に当ブログマスコットキャラクターの
はなまる
君の左なる元画像を変換して表示したものが下になりますので、
範囲選択反転、ブラウザの拡大機能を利用する抔して確認されてみられるのも一興と存知ます。